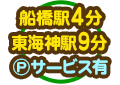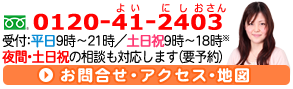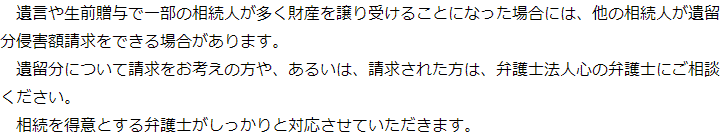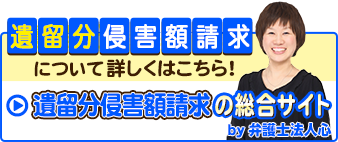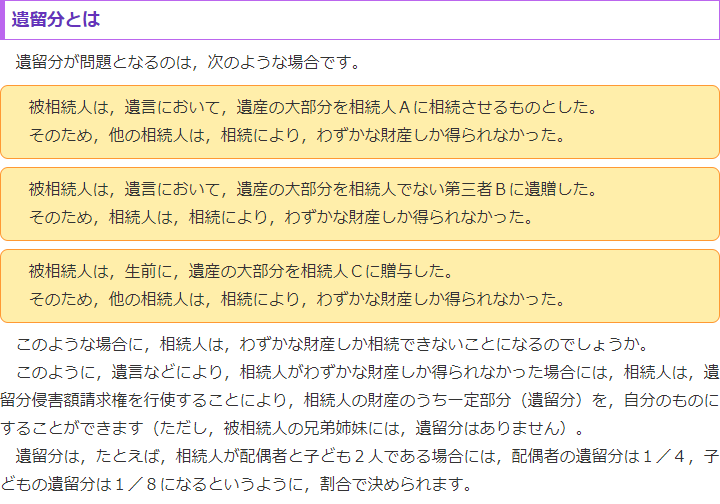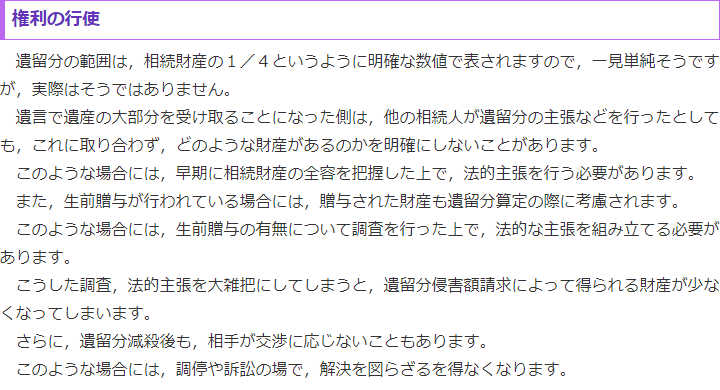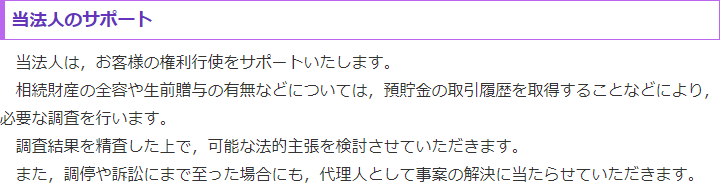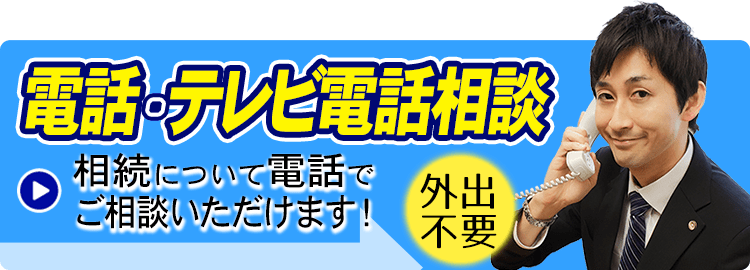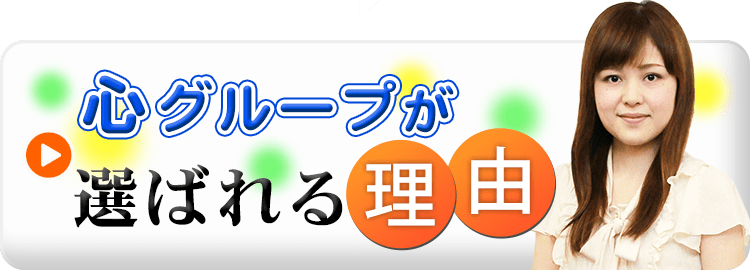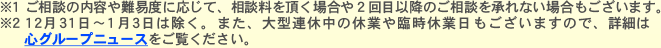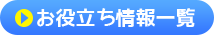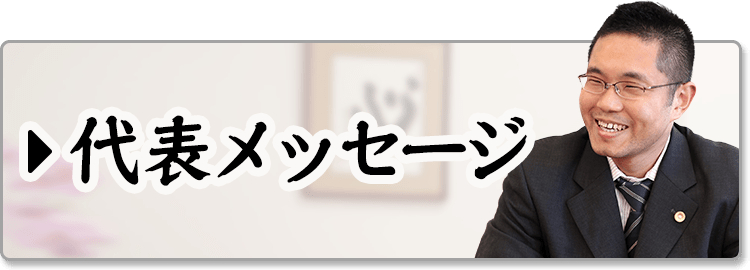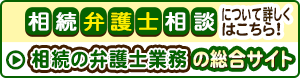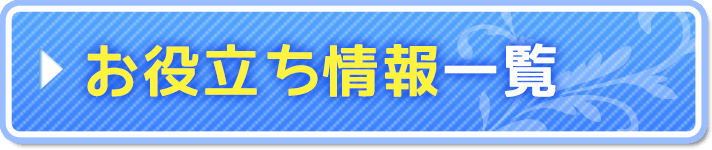遺留分侵害額請求
遺留分の計算方法
1 遺留分の計算の概要

遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産に、遺留分権利者が有する遺留分割合を掛け合わせることで計算できます。
遺留分権利者が有する遺留分割合は、総体的遺留分として定められた割合に、法定相続割合を掛け合わせることで算定されます。
以下、具体的に説明します。
2 遺留分算定の基礎となる財産
遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時点で有していた財産に、生前贈与をした財産を加え、債務を差し引くことで算定されます。
生前贈与した財産は、①相続開始時(被相続人死亡時)からさかのぼって1年以内に贈与された財産、②1年以上前の贈与のうち、被相続人と贈与を受けた人の両方が、その贈与によって相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合の当該財産、③不相当な対価で有償処分された財産であり、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってされたもの、④相続開始前の10年間に婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として相続人に贈与された財産が含まれます。
被相続人に債務がある場合、その全額を差し引くことができます。
具体的には、被相続人の借金や、医療費などの未払金が考えられます。
3 総体的遺留分
総体的遺留分は、遺留分権利者全員に対して保障されている遺留分の割合です。
具体的には以下の通りです。
なお、亡くなられた方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
⑴直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合には、総体的遺留分は3分の1です。
⑵上記以外の場合は、総体的遺留分は2分の1です。
4 個別的遺留分
個別的遺留分は、最終的に個別の相続人に割り当てられる遺留分の割合です。
遺留分を請求できる権利をもつ相続人が複数いる場合、個々の相続人が請求できる個別的遺留分の計算が必要になります。
個別的遺留分の割合は、上述の総体的遺留分に、法定相続割合を掛け合わせることで算定することができます。
例えば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合、総体的遺留分は、2分の1です。
配偶者の法定相続割合は2分の1なので、配偶者の個別的遺留分の割合は4分の1となります。
子の法定相続割合はそれぞれ4分の1なので、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ8分の1になります。
なお、遺留分権利者が1人のみの場合は、個別的遺留分と総体的遺留分は同じになります。
遺留分侵害額請求に関する専門家の選び方
1 遺留分侵害額請求に強い専門家(弁護士)を探すことが大切

結論から申し上げますと、遺留分侵害額請求に関する専門家を選ぶ際は、遺留分侵害額請求に強い弁護士を探すことが大切です。
実は、法律にはとても多くの分野が存在するので、ひとりの弁護士がすべての法律分野に精通することは、現実的には困難なのです。
遺留分侵害額請求を扱っている弁護士は多数いるかもしれませんが、メイン業務としてではなく、複数の分野の事件を扱ううちのひとつとして、遺留分侵害額請求を行っているだけであるということもあり得ます。
遺留分侵害額請求を取り扱っているといっても、必ずしも遺留分侵害額請求が得意な弁護士であるとは言い切れません。
そこで以下、遺留分侵害額請求に強い弁護士を選ぶためのポイントについて説明します。
2 遺留分侵害額請求の成否には経験の差が大きく影響する
遺留分侵害額請求は、相続に関連する法的な紛争のひとつです。
遺留分権利者が、遺留分を侵害している者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることになります。
遺留分侵害額を請求するうえで必要なノウハウは、大きく2つあります。
ひとつは、遺留分侵害額の計算です。
遺留分侵害額の計算はとても複雑です。
特に、生前に贈与または遺贈された財産の中に、不動産や非上場株式が含まれている場合には、遺留分侵害額請求の前提として、それらの評価額を算定する必要があります。
不動産や非上場株式の評価方法は多数あり、評価の方法によって評価額が大きく異なることもあります。
一般的に、評価額を高く算定するほど、請求できる遺留分侵害額は高額になりますので、遺留分侵害額請求の請求を行う弁護士が、財産評価の経験、ノウハウを豊富に有していることが重要になります。
もうひとつは、当事者間の交渉です。
遺留分侵害額請求は、相続にかかわる紛争の一種であり、数ある紛争の累計の中でも、個人の感情の影響を強く受けるものです。
被相続人と遺留分権利者、遺留分侵害者との人間関係や、過去の出来事等も大きく影響するため、単純な損得勘定のみでは円滑な交渉を進めることができないことが多いのです。
そのため、遺留分侵害額請求には、相続に関する交渉の経験、ノウハウが必要とされます。
3 遺留分侵害額請求に強い弁護士を探すためのポイント
遺留分侵害額請求に強い弁護士を探すための重要なポイントとして、今まで扱ってきた遺留分侵害額請求の数が挙げられます。
遺留分侵害額請求のための財産評価や、当事者間の関係性は、事件によって全く異なります。
遺留分侵害額請求を多く扱えば扱うほど、例外的なケースや困難な場面への対応の経験が積まれていきます。
そのため、遺留分侵害額請求に強い弁護士を探す際には、遺留分侵害額請求を集中的に扱っているのかどうか、年間で何件の遺留分侵害額請求を扱ってきたか等に注目するとよいでしょう。