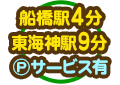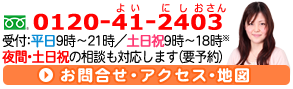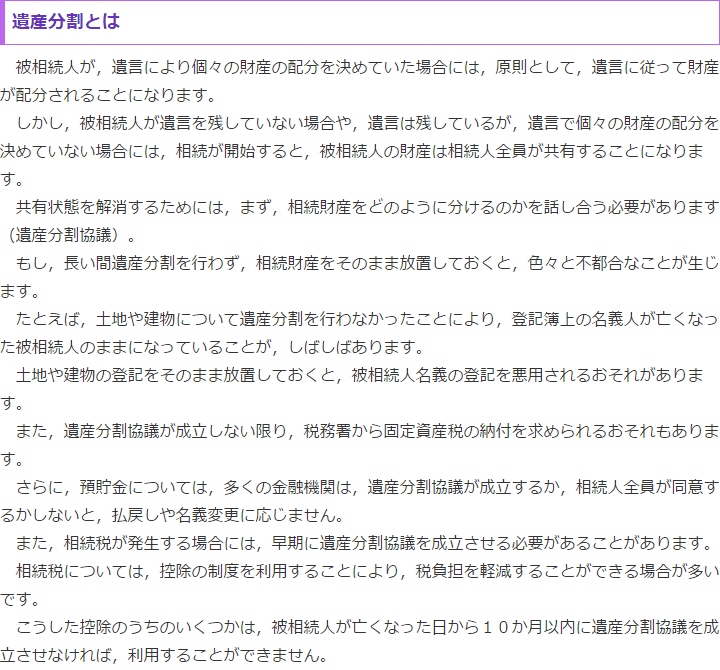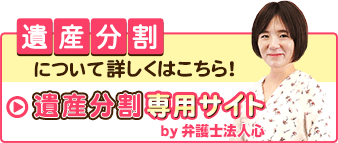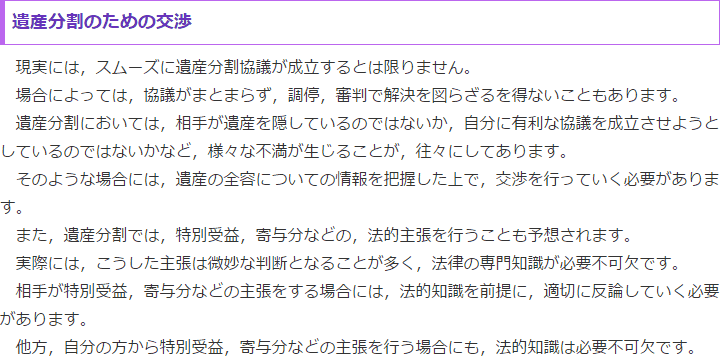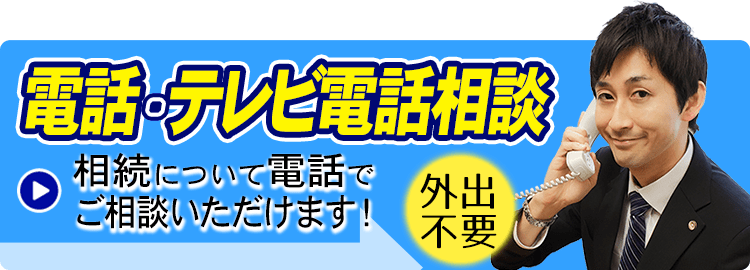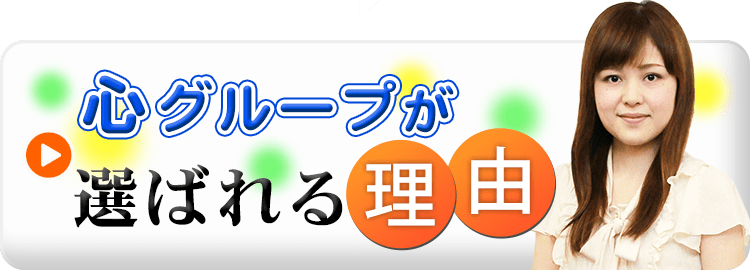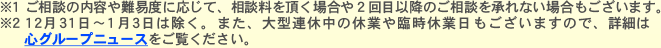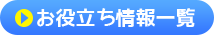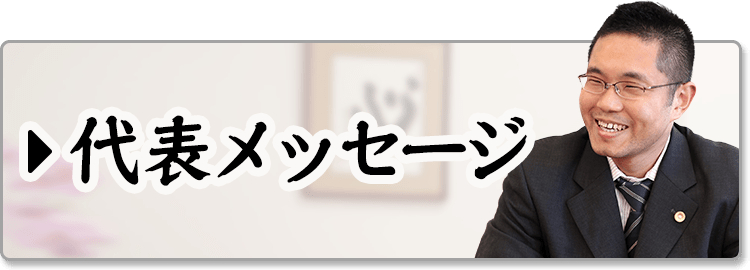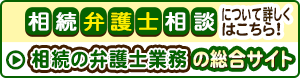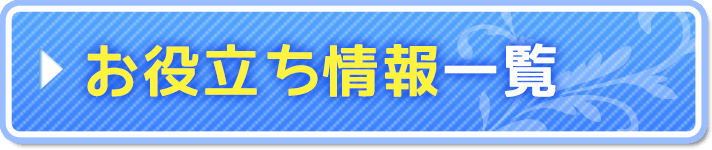遺産分割
遺産分割がまとまらない場合の流れ
1 遺産分割がまとまらないとどうなるのか

遺産分割は、原則として、まず相続人同士で話し合うことになります。
話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
それでも遺産分割が成立しない場合には、遺産分割審判を行うという流れになります。
以下、それぞれの段階について、詳しく説明します。
2 まずは相続人同士での話し合い
相続人の確定と相続財産の調査が済んでいることを前提に、まずどの財産をどの相続人が取得するかについて、相続人同士で話し合います。
ここで遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、遺産分割は終了します。
話し合いでは遺産分割がまとまらない場合や、連絡が取れないまたは返答をしない相続人がいる場合、次の段階である調停に進むことになります。
3 遺産分割調停・審判
遺産分割調停は、管轄の家庭裁判所に対して、調停の申立書等一式を提出することで申立てることができます。
調停申立に必要な書類としては、一般的に、相続財産に関する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記・固定資産評価証明書、有価証券の残高証明書等)、戸籍謄本類、相続人の住民票、収入印紙などが挙げられます。
遺産分割調停の申立てをすると、家庭裁判所において、調停委員を交えた話し合い(「期日」といいます)が行われます。
期日は、1~2か月に1回程度開催されます。
遺産分割調停が終了するまでに開催される期日の回数は、事案によって様々ですが、一般的には1~10回程度です。
調停の期日で無事話し合いがまとまった場合には、遺産分割の内容を記した調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。
また、調停の期日以外でも相続人同士が話し合い、遺産分割が成立した場合には、調停を取下げるということもあります。
話し合いが平行線となってしまった場合や、連絡がつかない相続人がいる場合、または不誠実な手段で遺産分割調停の進行を妨げる相続人がいる場合など、調停での話し合いが続けられないと判断された場合、家庭裁判所が遺産分割の内容を決める審判の手続きに移行することもあります。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
1 遺産分割協議書は相続手続きで必要

遺産分割協議書は、相続人が複数人いる場合に、どの相続財産をどの相続人が取得するかについて記載した書面です。
法律上作成が義務付けられているものではありませんが、預貯金の解約・名義変更や相続登記などの相続に関する手続きの際に必要となりますので、遺言がない場合には、実務上は作成が必須となります。
なお、遺産分割協議は相続人全員で行った上で、協議書は相続手続きに対応できる内容で記載する必要があります。
以下、詳しく説明します。
2 まずは相続人を確定させる必要がある
遺産分割協議は、法律上、相続人全員で行わなければ効果を生じないとされています。
そのため、遺産分割協議を行う前提として、相続人を調査し、確定させる必要があります。
あまり多くはありませんが、相続人の調査をした結果、相続人の大半が認識していなかった、疎遠な相続人がいることが判明するということもあります。
もし遺産分割協議書を作成した後に別の相続人の存在が判明した場合、再度遺産分割協議書の作成をやり直すことになってしまうので注意が必要です。
相続人は、ごく一部の例外を除き、通常は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、そこから相続人を追っていくことで確定させることができます。
被相続人が離婚、再婚をしている場合などは、相続人の構成が複雑になることもあるので、しっかりとした調査をすることが大切です。
また、代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、代襲相続人も確定させる必要があります。
3 相続の対象となる財産を特定できるようにする
1人の相続人がすべての財産を取得するような場合を除き、基本的には、誰がどの財産を取得するかについて、具体的に記載する必要があります。
相続財産についての記載が不正確であると、法務局における相続登記や銀行での預貯金の解約・名義変更手続きに支障をきたす可能性があるためです。
不動産については、登記事項証明書を確認し、地番や家屋番号などを正確に記載します。
預貯金については、口座のある銀行名、支店名、預金の種別(普通預金、定期預金など)、口座番号を記載しましょう。