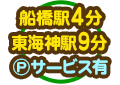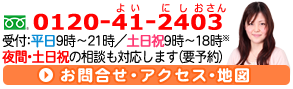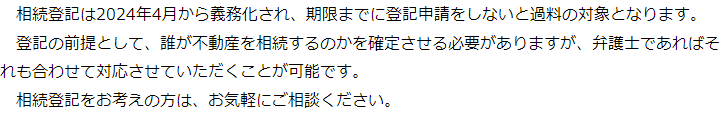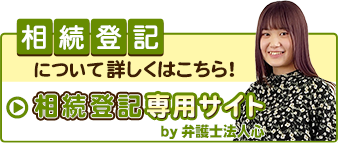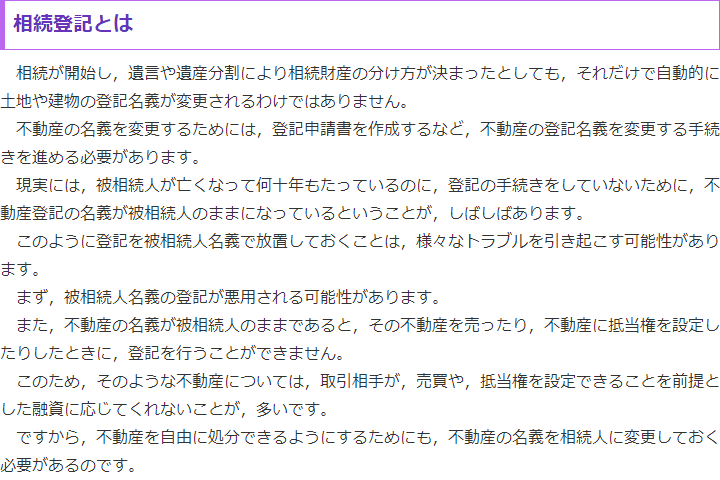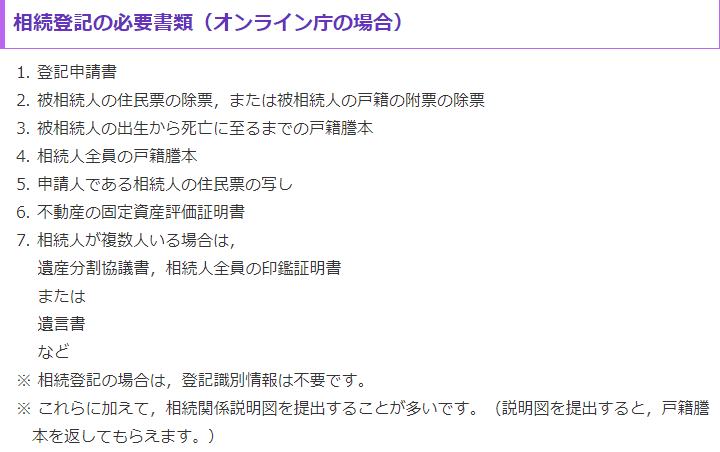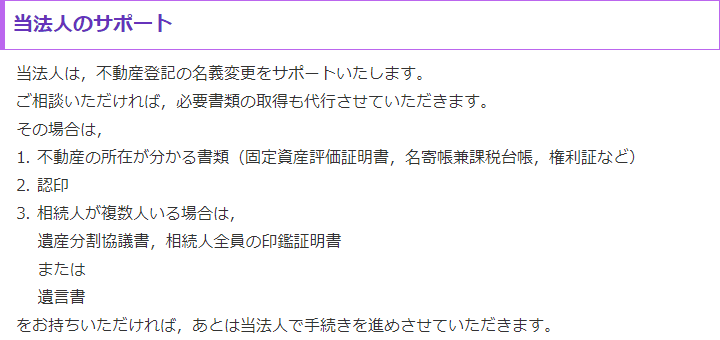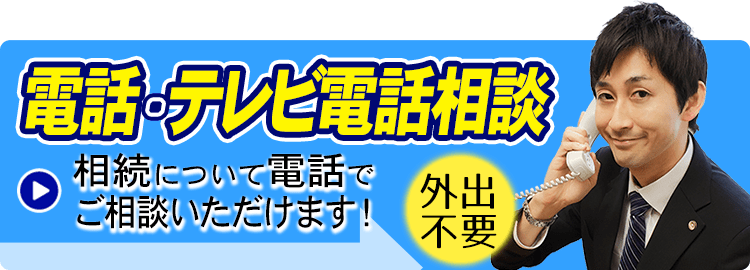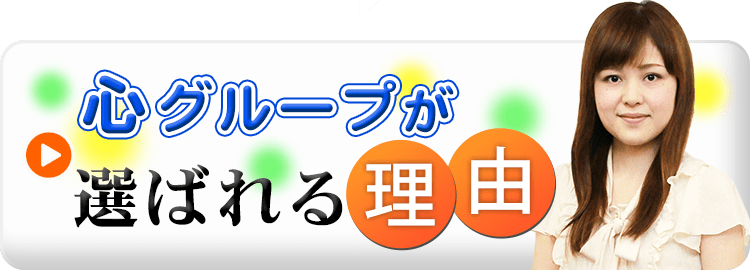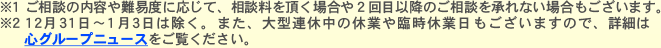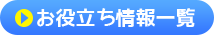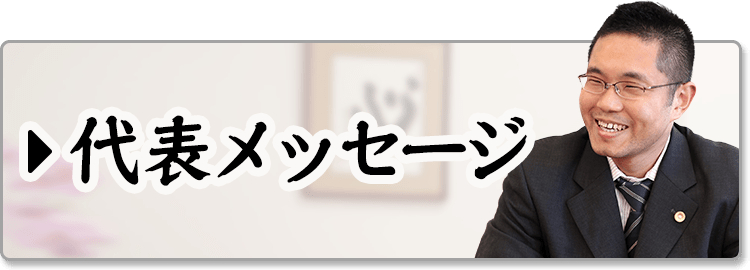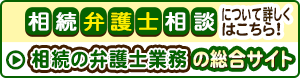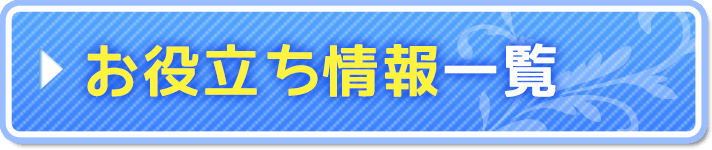相続登記
船橋駅の近くにある事務所
船橋や周辺地域にお住まいの方はどうぞご利用ください。こちらでは事務所所在地や地図、お問合せ先などをご確認いただけます。
相続登記が必要な理由
1 相続登記について

相続登記は、被相続人が所有していた不動産の所有権が、特定の相続人(複数の相続人による共有含む)に移転したことを、第三者に対して客観的に示すために必要な手続きとなります。
このことは、相続によって取得した不動産の売却や、当該不動産に担保権を設定する際に影響します。
また、2024年4月1日以降、相続登記が義務化されます。
以下、それぞれについて説明します。
2 相続によって取得した不動産を売却する場合
相続が開始した時点においては、被相続人の不動産の登記名義人は被相続人のままです。
遺産分割協議や遺言により、被相続人の不動産を取得する相続人が決まっているのであれば、理論的には、当該不動産の所有者となった相続人または受遺者は、当該不動産を売却する権限を持ちます。
しかし、不動産を売却する際には、取引の安全性を確保するという観点から、権利関係の来歴を正確に登記に反映する必要があります。
そのため、まずは被相続人から相続人に相続登記を行い、次いで、相続人から買主に所有権移転登記をする必要があります。
また、遺産分割協議や遺言によって相続人が不動産を取得したとしても、相続登記をしないと、法定相続割合を超える分については、第三者に対抗できません。
相続登記をする前に、第三者に対して法定相続割合を超える部分を売却されてしまった場合、権利の主張ができなくなってしまうことにも注意が必要です。
3 相続によって取得した不動産に担保権を設定する場合
相続税の納税資金調達など、何らかの事情によって、相続で取得した不動産に担保権(抵当権)を設定して金銭の借入をする必要が生じることもあり得ます。
この場合も、2と同様の事情により、先に相続登記を済ませておく必要があります。
4 相続登記の義務化
2024年4月1日以降は、相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をすることが義務となります。
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議成立の日から3年以内に相続登記をすることが義務づけられます。
注意するべき点としては、2024年4月1日以前に相続が発生したケースにおいても、原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があるということです。
遺産分割が紛争に発展してしまい、速やかに相続登記をすることができない場合には、一旦法定相続割合で相続登記をするか、または相続人であることを申告すれば相続登記をする義務を免れることができるという制度を利用することになります。
これらの義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
相続登記の流れと必要な期間
1 相続登記の流れと期間の概要

ご自宅などの不動産を所有していた方がお亡くなりになり、相続が発生した場合、法務局で不動産の相続登記を行う必要があります。
遺産分割協議によって被相続人の不動産を取得した相続人が、自らの名義に変更するという手続きが相続登記です。
なお、相続人が一人しかいない場合には、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議をするためには、前提として、相続人を確定する必要があります。
まとめますと、相続登記をする流れは、相続人を確定し、(相続人が複数いる場合)遺産分割協議を終えたら、管轄の法務局に対して登記申請をするということになります。
相続登記に要する期間は、一般的には2~4か月程度となります。
以下、具体的に説明します。
2 相続人の確定と遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となります。
そのため、まずは相続人を調査し、確定させる必要があります。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、かつ相続人の現在の戸籍を収集します。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍も取得します。
そのうえで、どの相続人が被相続人の不動産を取得するかを決めて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に不動産の情報を記載する際には、登記を見ながら、地番や家屋番号等を正確に反映させます。
遺産分割協議書ができあがったら、相続人全員で署名と押印をします。
押印は実印を用い、印鑑証明書も添付します。
相続人が一人だけの場合には、被相続人の不動産は当該相続人が自動的に取得することになりますので遺産分割協議書の作成は不要ですが、相続人が一人だけであることを証明するため、相続人の確定作業は必要になります。
相続人の調査確定には、一般的には1か月程度要します。
そして、遺産分割協議書の作成にも1か月程度要すると考えられます。
この2つは、ある程度並行して進めることができます。
3 管轄の法務局に相続登記の申請を行う
相続人の確定と、(相続人が複数いる場合)遺産分割協議書を作成したら、相続登記の申請書を作成し、管轄の法務局に登録免許税と一緒に提出します。
管轄となる法務局は、相続登記の対象となる不動産の所在地で決まります。
参考リンク:法務局・管轄のご案内
まずは、相続登記の対象となる不動産がある都道府県の法務局のページにアクセスし、次に当該不動産がある市町村を管轄する支局・出張所を確認するとよいでしょう。
書類を法務局に提出してから、一般的には1~2か月程度で相続登記は完了します。