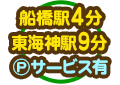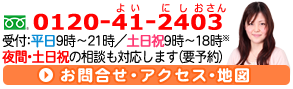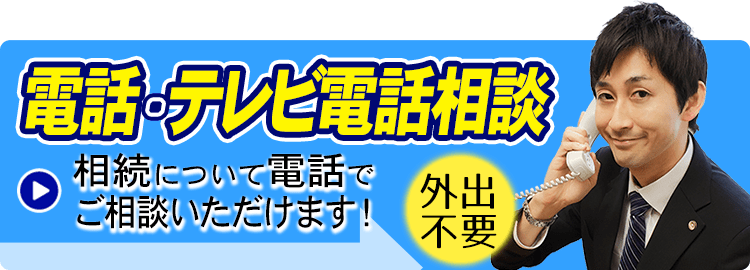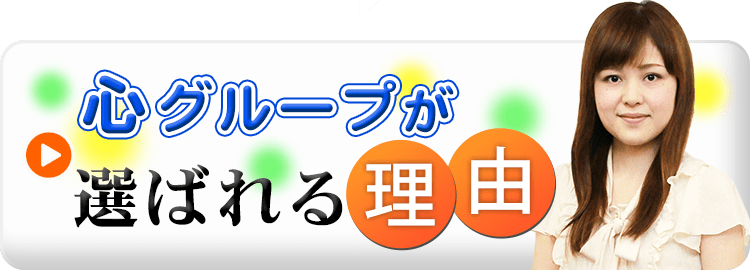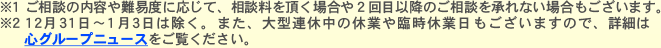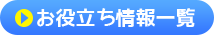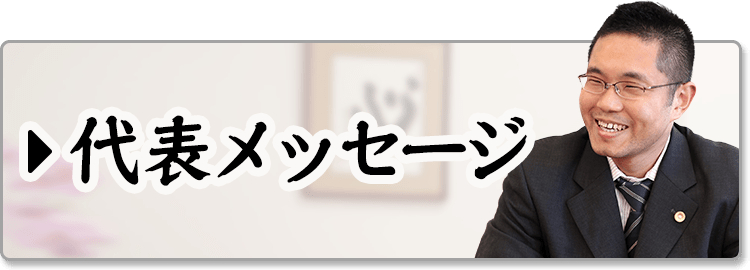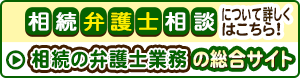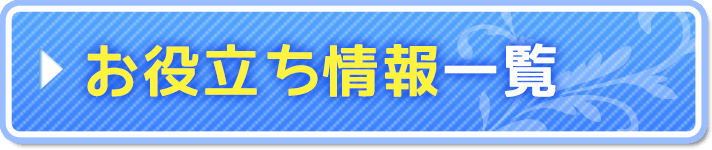相続財産調査
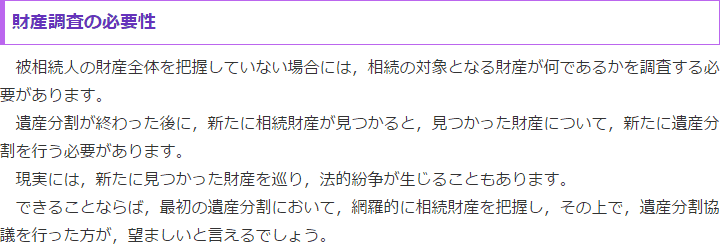
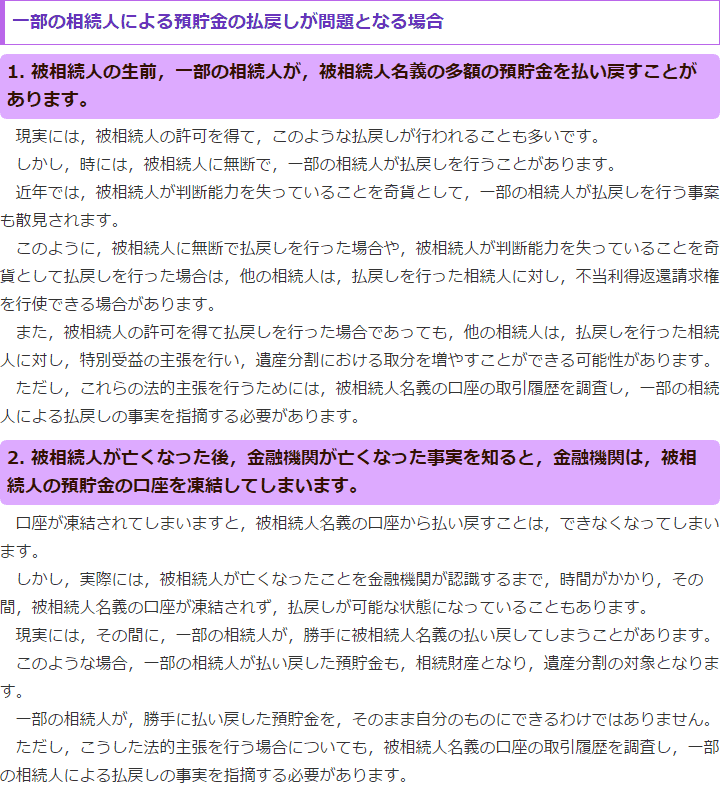
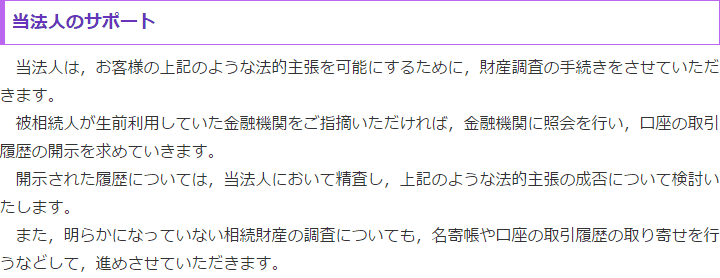
相続財産の調査方法
1 相続財産の調査方法の概要

相続財産(債務含む)は、一般的には、被相続人(お亡くなりになられた方)が持っていた書類や資料等をもとに、地道に調査をしていく必要があります。
被相続人の方が、生前は成年被後見人であった場合などは、財産目録によりある程度相続財産を把握することが可能です。
被相続人が生前に正確な財産目録を作成していた場合には、相続財産の調査を行う必要はあまりありませんが、実務上は、そのようなケースは多くはありません。
相続財産に該当するものとしては、現金や預貯金、自宅などの不動産、有価証券(株式、投資信託等)、骨とう品などの高価な動産が挙げられます。
また、相続債務としては、借入金や未払金の調査も必要になります。
相続税申告が必要と考えられる場合、死亡保険金も相続財産とみなされるので、正確な金額を把握する必要があります。
以下、これらの財産等の調査方法について、具体的に説明します。
2 現金や預貯金の調査
まず、現金は被相続人の方の財布、机の引き出し、金庫がある場合には金庫の中等を調べます。
葬儀費の準備等のため、お亡くなりなる直前に多額の引き出しをした場合には、その引き出した金銭も相続財産に該当します。
預貯金については、基本的には、通帳を調査することから始めます。
通帳が見つからない場合には、金融機関からの郵送物やキャッシュカードなどを確認し、当該金融機関へ口座の有無と残高の照会をします。
通帳等が存在しないネット銀行の口座の有無を調べる場合には、口座開設時の郵送物等がないか確認します。
3 不動産の調査
まず、被相続人の方宛ての、固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書を探します。
さらに被相続人の不動産が存在する自治体の固定資産課税台帳(名寄帳)を取得することで、納税通知書に記載されていない不動産の存在が判明することもあります。
そのほか、被相続人の方の不動産の権利証があれば、その内容を確認し、納税通知書等に記載されていないものであれば、登記を取得し、相続開始時点で被相続人の所有に属していたか否かを確認します。
4 有価証券(株式、投資信託等)の調査
まず、被相続人宛ての取引報告書や残高報告書がないか確認します。
取引報告書等が見つかったら、発行元の証券会社等に連絡をし、被相続人がお亡くなりになられた時点での残高や評価額を紹介します。
ネット証券の場合、取引報告書等が送付されないこともあります。
この場合には、口座開設時の資料等を探し発行元の金証券会社等に対して残高と評価額の照会を行います。
5 骨とう品などの高価な動産の調査
絵画や日本刀などの美術品や、金のインゴットなどが該当します。
これらのものは、銀行等の貸金庫内にあることもありますので、開扉して中を確認します。
自動車がある場合には、車検証を確認し、同じ型番の自動車の中古車価格などを調査します。
6 相続債務の調査
被相続人の方がローンなどを組んでいる場合には、金銭の借入に関する契約書等がないか確認します。
もし契約書等あった場合には、貸主に対し、残債務の有無等を確認します。
被相続人の方宛の郵送物の中に、貸金業者やクレジットカード会社からの郵送物があり、借入金や立替金に関する記載がある場合、相続債務が存在する可能性があります。
この場合には、貸金業者やクレジットカード会社へ連絡し、正確な債務額を提示してもらいます。
そのほか、被相続人の方の通帳を確認し、公共料金の引き落としがある場合、被相続人がお亡くなりになられた時点で未払いのものがないか確認します。
7 生命保険の調査
相続人の方等が受け取ることができる死亡保険金の有無と金額を確認します。
具体的には、保険証書や、保険会社から被相続人宛に定期的に送付される契約内容確認書面等を探します。
これらの資料をもとに、被相続人がお亡くなりになられた旨を生命保険会社へ連絡し、生命保険支払通知書等を送付してもらいます。