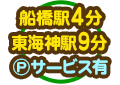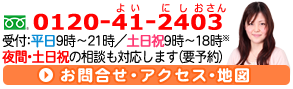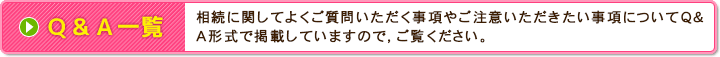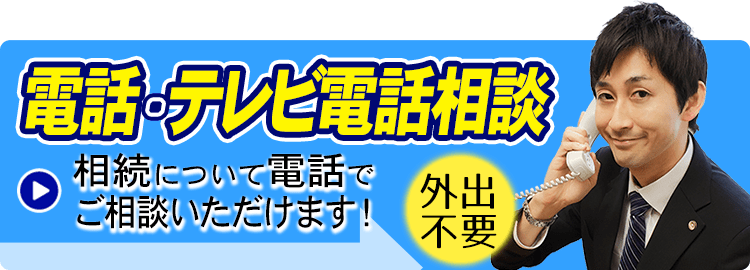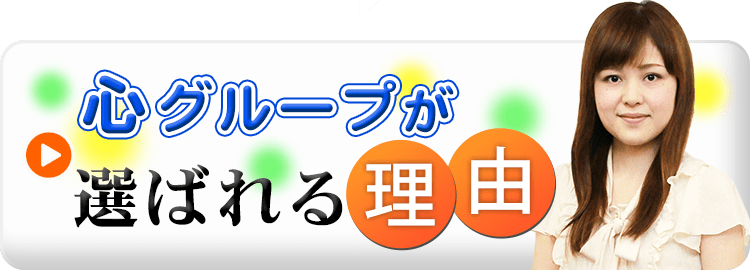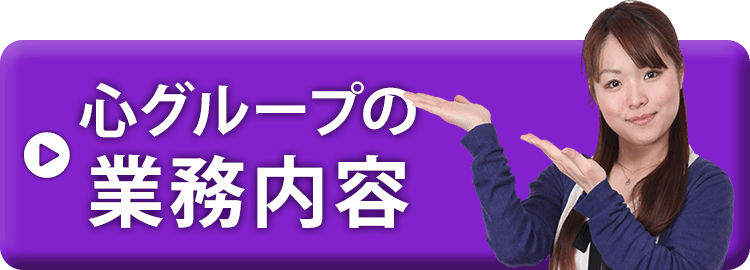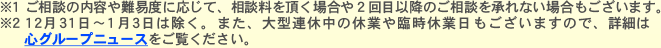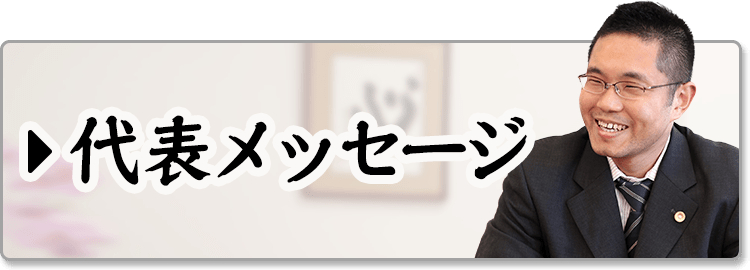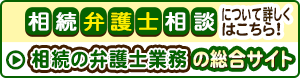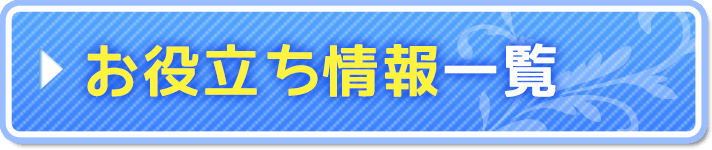事業承継の注意点
1 事業に関する財産を後継者に相続させること
⑴ 相続時のトラブル
事業承継について最も重要なことの1つは、事業に関する財産をその事業を承継する後継者に確実に承継させ、事業を継続させ、株式なども分散させずに会社の決定権を確実に特定の後継者に遺すことです。
しかし、法律上法定相続人が複数人いる場合は、法律によって定められた割合によって相続分が決められており、後継者となる相続人が事業に関する財産を集中して相続しようとすると、相続人全員の合意が必要となるのが原則です。
事業に関する財産以外に金銭が多くあれば、遺産分割協議において、事業用の財産相続しない他の相続人に多く現金を渡すなどして、不公平を解消しつつ、事業を承継するということも可能ですが、金銭のような調整できる財産が少ない場合は、その調整が困難になることがあります。
また、後継者としたい人が法定相続人でない場合は、相続において事業承継ができず、相続人間と後継者となる人とで、承継の手続を取る必要が生じることがあります。
⑵ 対策例
複数の相続人がいる場合は、遺言書を作成し、後継者となる人に事業用の財産を相続させるように指定しておくことが有効です。
遺言書を作成しておくことで、相続財産を細かく、誰に、何を相続させるかを指定することができますので、後継者となる人に事業に関する財産を相続させることができます。
また、遺言書であれば、相続人でない人に対しても事業財産を相続(遺贈)することができますので、相続人以外の人を後継者とすることも可能です。
他の手段としては、事業承継がそもそも相続に問題を生じさせないように、事業に関する財産を後継者となる人に生前から事業に関する財産を贈与しておくことも有効です。
2 相続人間での遺留分の争いが生じることもある
⑴ 遺留分のトラブル
遺言書や生前贈与によって、後継者となる人に事業に関する財産を相続や贈与させたとしても遺留分の問題が生じる場合がありますので注意が必要です。
遺留分とは、被相続人(亡くなって財産を渡す人)が遺言書等で財産の分け方を決めたとしても、一定の相続人に認められる、相続によって取得することが保障された権利のことです。
被相続人が特定の人に対して多くの財産を相続させたとき、遺留分を有する相続人は、侵害された遺留分の価額について請求することができます。
つまり、後継者に対して財産を多く残そうとした結果、その後継者が遺留分を侵害している問題が生じてしまうことがあるということです。
もし、後継者が遺留分を金銭で支払えない場合は、事業のための財産を売却するなどしなければならなくなり、事業に支障を及ぼしてしまう場合があります。
⑵ 対策例
贈与をした時期等によっては、遺留分の計算に含まれないように財産を贈与することができます。
そのため、事業承継を相続に持ち越さないようにするために生前贈与をする時期を早めにすることは、同時に遺留分対策になる場合があります。
他にも、単純ですが、遺留分侵害額を請求されたとしても、支払えるように資金準備をしておくということも有効です。
そのほか、遺留分対策は多岐にわたり、各人ごとに最も有効な手段が異なり、また、遺留分対策にならない場合もありますので、遺留分対策は相続に詳しい弁護士などの専門家を交えて行うことが重要です。
3 会社の債務と個人保証
⑴ 想定外の債務がある場合のトラブル
後継者を相続人以外の人を選んでおき、自分が亡くなった後は、家族と会社(特に会社の債務関係)を切り離したいと思っていたとしても、家族が債務を負ってしまう場合があります。
つまり、会社が融資を得る際などに、経営者が個人保証を行うという場合があり、これは事業等とは別に、被相続人個人の債務として処理する必要があります。
債務については、遺言書で「●●が債務を負う」というように後継者となる人が債務を負担するように遺言書を作成したとしても、法定相続分とおりに、債権者から請求される場合があり、家族が家などを手放さなければならなくなることがありますので、注意が必要です。
⑵ 対策例
遺言書で、事業に関する財産を後継者に対し、遺贈した上で、家族には、相続放棄の手続を行ってもらう、という方法があります。
相続放棄をすることによって、経営者の方が負っていた個人保証についての債務を負わなくてもいいようになります。
ただし、相続放棄は基本的に、相続の開始を知ってから3か月以内に管轄の家庭裁判所に対し、手続きを行う必要があります。
その期間を経過してしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまいますので、そのような対策をすることを希望する場合は、事前にご家族との話し合いが必要となります。
また、相続放棄をすると、債務だけでなくほかの被相続人名義の家などの財産も相続せきなくなるため、その点でも注意が必要です
ほかにも、債務返済に備えて生命保険を利用するという方法もあります。
4 税金に関する注意点
⑴ 事業承継時の税金のトラブル
事業承継が発生するとき、事業の規模によっては、大きな税金(贈与税や相続税)が発生する場合があり、承継する側の人にとって大きな負担となり、事業にも影響を及ぼす場合があります。
そのため、事業承継に備えて、事前にどれくらいの税金が発生するかについても注意が必要です。
⑵ 対策例
税理士に相談し、どのような税金がどれくらい発生し、備えなければならないかについて把握し、事前に対策を行うことが重要です。
その上で、税金の支払いに耐えるだけの資金を準備しておくことが有効な対策となる場合があります。
また、事業承継時に一定の資産については、贈与税や相続税の納税を猶予する制度もあります。
参考リンク:国税庁・事業承継税制特集
こうした事業承継時に有利に働く税制もありますので、事業承継について考える際には、事業承継に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。