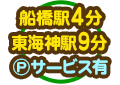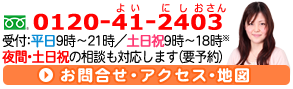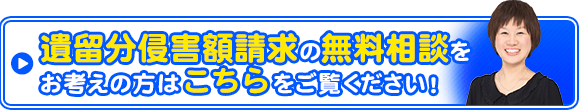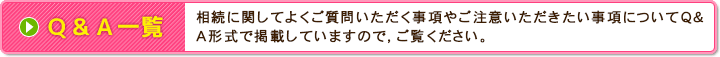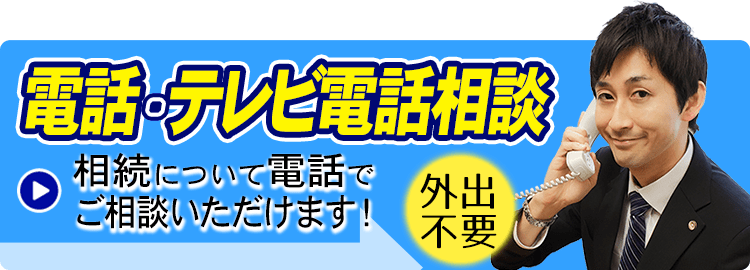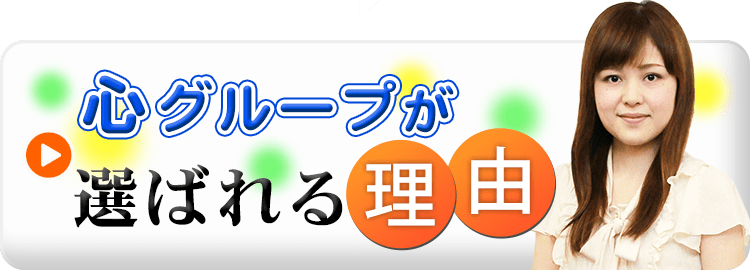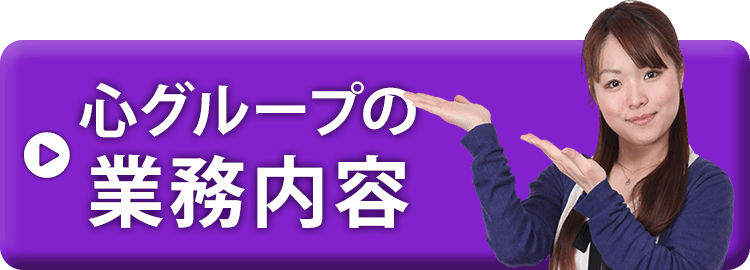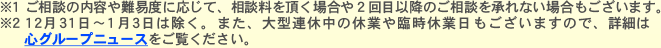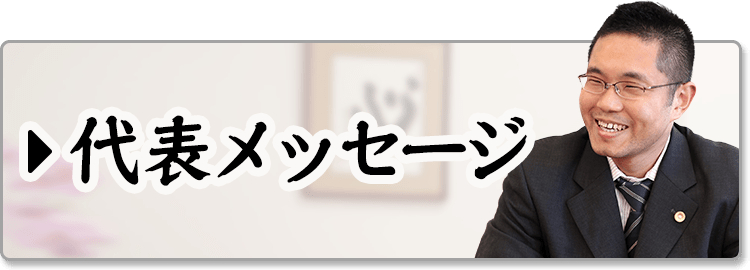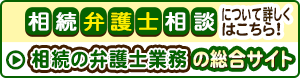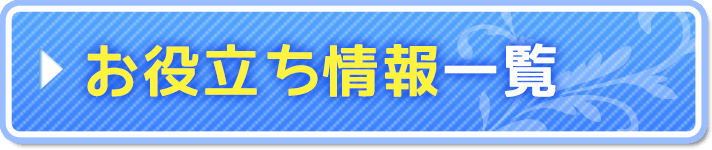遺留分を請求された場合
1 原則としては、支払う必要があります
遺留分を請求する旨の内容証明郵便が送られてきた場合、どう対応したらよいか分からずお困りの方や、本当に支払わなければならないのかと疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
結論から申し上げますと、遺留分を請求された場合、原則として法律で定められた範囲で、遺留分侵害額の支払いに応じる必要があります。
遺留分は、相続財産のうち、一定の相続人に対して最低限保障される割合であるためです。
以下、遺留分を請求された場合の対応について、詳しく説明します。
2 遺留分の請求を受けた場合の対応
⑴ 話し合い等による解決
まず、遺留分の請求を受けた場合には、支払う金額や支払い時期・方法等について話し合いをします。
その結果、合意ができた場合には、合意内容に従って支払いをして終了となります。
また、遺留分の請求は、遺留分を侵害する内容の遺言が存在する場合に発生します。
そして、遺言があったとしても、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議をすることが可能です。
そこで、改めて遺留分の請求をした相続人を含め、遺産分割協議をするという方法もあります。
⑵ 遺留分侵害額請求調停が申し立てられた場合
話し合い等では解決しない場合、遺留分の請求をした者が遺留分侵害額の支払いを求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることがあります。
調停が申し立てられた場合には、必要な書類を提出し、期日に家庭裁判所に出廷するなどの対応をする必要があります。
調停は、あくまでも家庭裁判所を介した話し合いですので、調停の結果、合意に達することができれば、合意内容に従った支払いを行うことで解決します。
⑶ 遺留分侵害額請求訴訟が提起された場合
調停でも解決しない場合、遺留分の請求をした者が民事訴訟を提起することもあります。
この場合、民事訴訟のルールに従って、主張立証活動等を行う必要があります。
訴訟が提起されたとしても、訴訟外で遺留分の支払いについて合意することができれば、訴訟が取下げられることもあります。
3 遺留分侵害額請求権の消滅時効について
遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で、時効により消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
そのため、遺留分の請求を受けた時点で、時効によって消滅していないかどうかもまずは確認する必要があります。