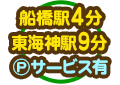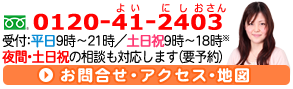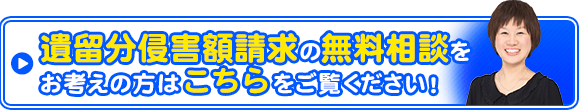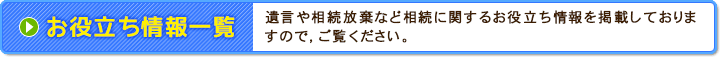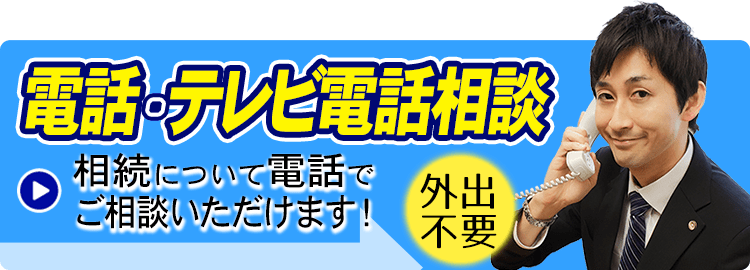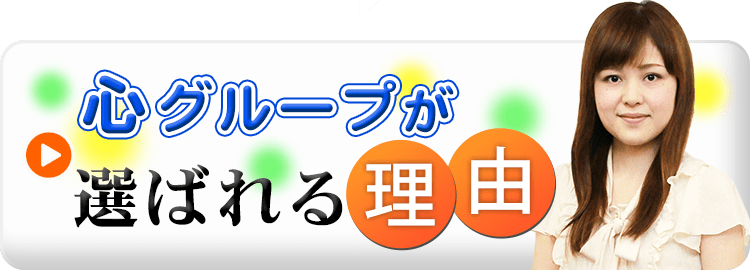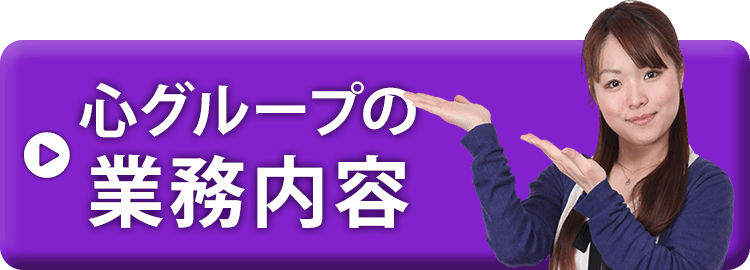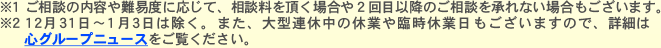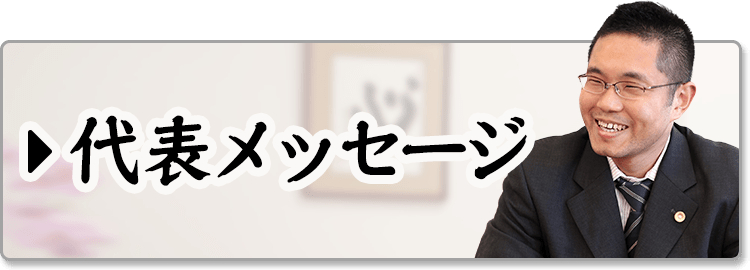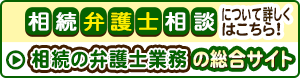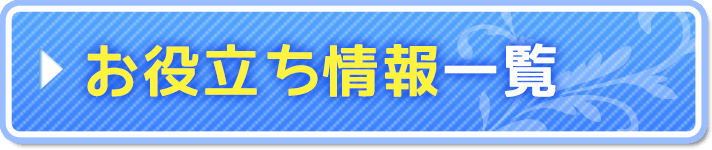遺留分の放棄についてのQ&A
遺留分の放棄とはどのような手続きですか?
相続人には、相続が発生した際に、遺産の最低限の取り分として、遺産のうちの一定の割合を取得することが保障されています。
この一定の割合のことを遺留分といいますが、遺留分の放棄は、この遺留分を被相続人となる方の生前になくしてしまう手続きです。
遺留分の放棄は、相続が開始される前に、遺留分を有する(推定)相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所の許可を得ることで実現します。
参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可
遺留分の放棄は相続の開始前にしか行えないのですか?
家庭裁判所における遺留分の放棄の手続きは、相続の開始前(被相続人となる方の生前)にしか行うことができません。
【参考条文】(民法)
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
(第2項略)
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
ただし、相続の開始後(被相続人がお亡くなりになられた後)であっても、遺留分をなくすことはできます。
相続の開始後に遺留分をなくすためには、特に手続きをする必要はなく、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以上経過することで、遺留分侵害額請求権が時効により消滅します。
【参考条文】(民法)
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
遺留分の放棄は相続放棄とは違うのですか?
遺留分の放棄と相続放棄は、混同されることがありますが、法律的には全く異なる手続きです。
遺留分の放棄は、先述のとおり相続開始前にしか行えませんが、相続放棄は逆に相続開始後でないと行うことができない手続きです。
また、遺留分の放棄をした場合であっても、相続人としての法的地位が失わることはありません。
これに対して、相続放棄をした場合には、はじめから相続人ではなかったことになります。
遺留分の放棄が許可されるのはどのような場合ですか?
遺留分の放棄は、家庭裁判所に申立てるだけで実現できるというものではありません。
遺留分は相続人の生活の保障のために設けられた、遺言によっても奪うことができない最低限の遺産の取り分であることや、他の親族等に強要されて遺留分の放棄をさせられてしまう可能性が存在することから、家庭裁判所が審査をしたうえで、放棄をすることが相当であると認めた場合のみ許可されます。
具体的には、①遺留分を放棄するだけの合理的な理由があるか、②遺留分の放棄をしようとしている者にすでに十分な代償が支払われているかという観点で判断されるとされています。
また、これらは、遺留分の放棄が本人の意思であることを裏付けるものでもあります。
例えば、被相続人になる方が会社経営者であり、相続によって会社の株式が分散してしまうことを防ぐため、特定の相続人にすべての株式を相続させる必要があるというケースが考えられます。
この事情は、遺留分の放棄をする理由としては合理的なものであると考えられます。
実務的には、会社の株主名簿などを用いて、株式の保有者の状況を疎明することになります。
また、このケースにおいては、会社の株式を含む財産の大部分を、特定の相続人に相続させる旨の遺言を作成すると考えられます。
そのため、遺留分を放棄した相続人は、会社の株式はもちろん、その他の財産もほとんど受け取ることができないことが想定されます。
そのため、遺留分を放棄する前に、生前贈与がなされているなど、すでに十分な利益が保障されていることについて、贈与契約書などを以て疎明することが考えられます。
遺産分割協議書の作成についてのQ&A 生前の相続放棄に関するQ&A