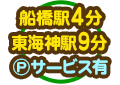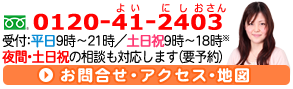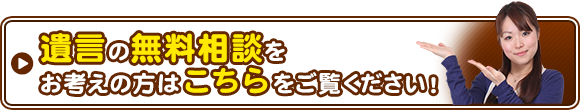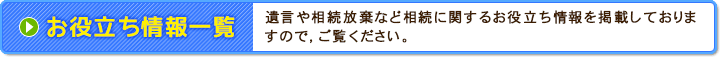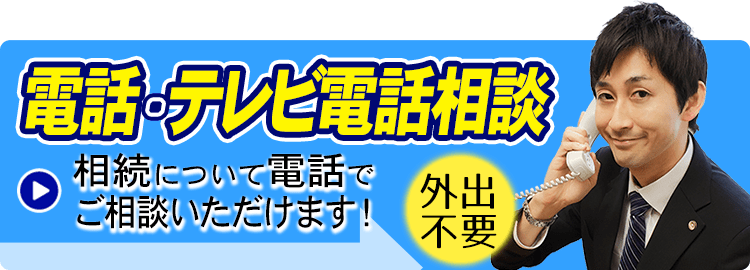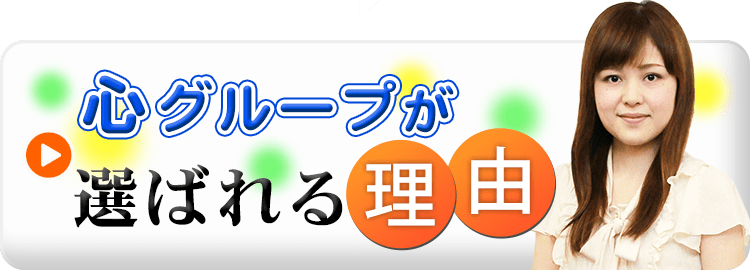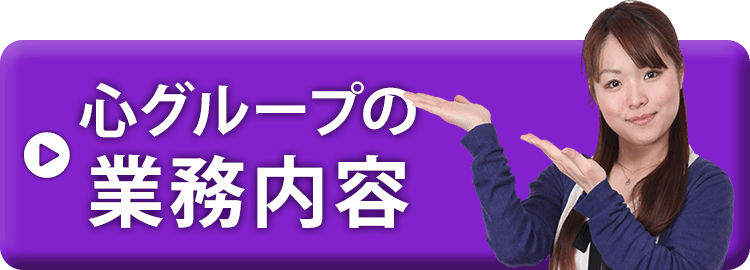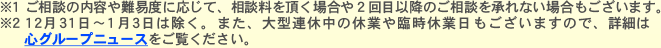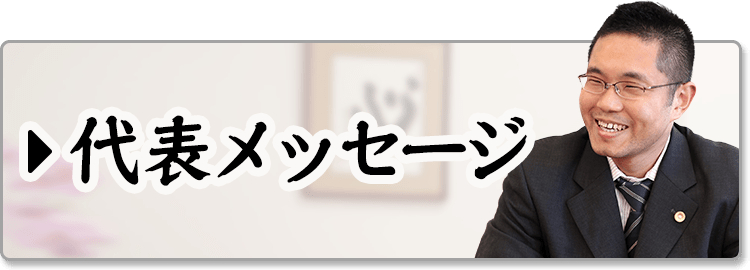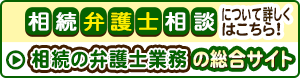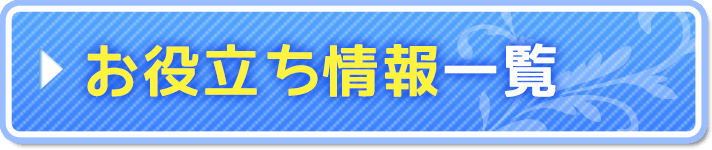遺言の効力に関するQ&A
遺言があったら、遺言の内容に必ず従わなければなりませんか?
相続人、受遺者全員で合意をすることができる場合には、遺言の内容とは異なる内容で、改めて遺産分割協議を行うこともできます。
ただし、遺言者は、遺言で相続開始のときから最大5年間、遺産分割協議をすること自体を禁止することができます。
遺言に遺産分割禁止の記載がある場合には、禁止期間を経過してからでないと遺産分割協議をすることはできません。
また、遺言執行者が選任されている場合には、その遺言執行者の同意が得られないと遺産分割協議をすることはできません。
受遺者や遺言で指定された相続人が先に死亡していたらどうなりますか?
受遺者や遺言で指定された相続人が、被相続人より先に死亡していた場合、原則としてその部分の遺言は無効となります。
なお、被相続人より先に死亡していた方に相続人がいた場合であっても、当然には代襲相続は発生しないということに注意が必要です。
(最高裁平成23年2月22日判決より一部抜粋)
「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた指定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成時の状況及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が上記の場合には、当該指定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生じることはないと解するのが相当である。」
受遺者や遺言で指定された相続人が被相続人より先に死亡していた場合に、受遺者や遺言で指定された相続人の子に遺贈ないし相続をさせたいのであれば、その旨を記載した遺言を作成するということもあります。
遺言の効力はいつから発生しますか?
遺言の効力は、原則として遺言者が死亡した時に発生します。
例外として、遺言に停止条件が付されていた場合は、その条件が遺言者の死亡後に成就した時に遺言の効力が発生します。
遺言執行者の選び方に関するQ&A 遺産分割協議書の作成についてのQ&A